|
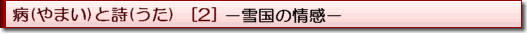
元国立環境研究所所長 大井 玄
地球温暖化のため今年二月の平均気温は史上最高であったそうな。小学、中学生時代を過ごした秋田でも雪はほとんど積もらなかったという。
老来とみに寒がりになったわが身にとって、暖冬のニュースは朗報であってもおかしくない。「おら、ひやみこきになってしまって」と、これも小中の同級生だった家内と秋田弁でふざけ合ったりする。「ひやみこき」とは寒がりで働かない者のことだ。ところが口とは反対に、寒くて雪の多かった「昔の故郷」をなつかしんでいる自分に気づく。
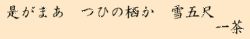
やがて戦火につつまれるだろう東京を離れて、父親が新しく赴任する秋田市に移ったのは昭和十九年夏、小学三年のときだった。市の郊外の北・西・南と三方に広がる秋田平野は一面の稲田で、秋にはきらきら光る黄金色の海と化した。しかしその冬は、六十年ぶりの豪雪となり、市の北西端にあるわが小学校は、雪を運ぶ風が直接吹きつけるため、北西に面した校舎の二階の屋根に至るまで雪に埋もれてしまった。
吹雪はすさまじかった。わが家から学校へはナワテと呼ばれた畦道をニキロほど歩いて通うのだが、強風を避けるにはできるだけ大人の背の後ろについて、その足どりを見ながら歩くのだった。防空頭巾をかぶるため視界がせばめられており、吹雪の中で方向を見失いがちである。実際、時として雪道で凍死者の出るような場所だった。吹雪が来るのは北西、日本海の方向から来る風がひゅうひゅうという音をたて始めることで判る。その方を見ると地平線に灰色がかった帯が現れ、それが次第に丈を加えながらこちらへ進んでくる。スピードはぐんぐん高まり、帯はいつのまにか雪の絶壁となっている。そこまで来たと思う瞬間、私たちは飲み込まれてしまい、まるで高波の底に入ったように雪片は口を鼻を目を塞ぎ、息をするのも苦しくなる。
夜、悲鳴をあげるような風の音を聞きながら寝るとき、雪女の民話を思い出しながら小便に起きないよう念ずるのだった。なにしろ便所は母屋から離れた場所にあり、藁の雪ぐつを履かないとたどり着けないのである。だから雪のしきりに降る夜などは、母屋の庇の下で雪に放尿するのだった。
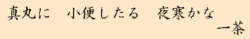
こんな北国の「少年期刷りこみ」があったからだろうか、長野県佐久市で「寝たきり老人呆け老人」の宅診を始めたとき、まるで故郷に戻ったような懐かしさを覚えたのは。四季の移り変わりは、冬の厳しさによって一層鮮やかになる。凍てつく寒さと雪景色があるからこそ芳しい春の陶酔が生れる。
しかし佐久で相手をしたのは終末期に入った人だったから、そこには口に出さぬものの無常の感覚が常に在った。「寝たきり老人呆け老人」の数は多く、再度訪問するのは原則として一年以上経ってからになる。したがって次の順番が巡るころには亡くなっている人が何人もいた。彼らはどういう想いで桜を眺めたのだろうか。まだ若かったその頃は、彼らの胸のうちも想像はできても、実感することはできなかった。
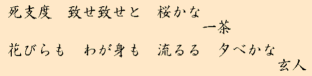
雪国といっても秋田の人と信州の人とは気質がずい分違っていた。忍耐づよい点では共通するものの、秋田の人は口が重く、話べただった。それなのに見栄を張る面がある。これに対して、長野では論理的に話をする人が多く、しかもしたたかな根性というか反骨精神があり、芸術的感覚に恵まれているという印象が強い。俳人一茶の根性や感性を受けついだ人々の層の厚さを見ると、それが土地の遺伝要因によるものか、それとも信州という戦いや人馬の動きの活発な地域の歴史によるものかと考えてしまう。
一茶は継母にいじめられ、十四歳で口減らしのため江戸にだされて貧窮生活を送り、故郷に帰ってからも家庭に恵まれることがなかった。しかも情の薄かった父に対する彼の看病は献身的だった。不眠不休の介護、父に食べさす1個の梨を遠方まで求め歩いた。その父への思いや可愛がっていた子の死への悲しみを托した句を読むと、現代日本人の心性の変化に荘然とする。

そして
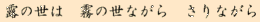
世界一低い乳児死亡率そして世界一長寿の日本では、「露の世」という感慨は消失したように見える。しかしその状態をしあわせと感じないのが、人間心理の不思議であろう。
Que Sera Sera VOL.48 2007
SPRING
|
![]()