|

元国立環境研究所所長 大井 玄
終末期医療、特に在宅での看取りを勧める運動というと、なにやら身体的な問題から魂の問題にいたる茫漠たる領域を想像されよう。もちろん実存的な悩みも有るが、やがて寝たきり状態も迫りつつある人たちが経験する一大問題は、排便のコントロールである。
「なに、緩下剤を使えばいいじゃないの」というのは「快食、快便」族の驕りである。もちろん緩下剤はいろいろある。試しにある緩下剤を一粒毎晩飲むと下痢してしまう。しかも「締り」が緩くなっているので、便意を感じてトイレに行くまでに「ちびって」しまうのである。しからば「半粒」を服用すると、あんなに敏感だった大腸がウンともスンとも動いてくれない。では一粒を一晩おきに飲む。ところが今度は下痢と便秘が不規則に交代するようになった。自分に合った薬と服用パターンを発見するに至るまでには、他人には伝えられない工夫と試行錯誤がある。
九十歳になる女性がいた。腰痛と膝の痛みで便所にいざっても行けず寝たきりだった。息子が日中働きに出かけており、おしめをつけたまま放置されている状態である。困ったことに緩下剤を少し使うだけでも下痢になり、止めると便秘する。便は出ていたほうがいいので下痢便を放置していたら皮膚炎をおこし、彼女のお尻から陰部が無残に爛れた。もちろん薬を塗布するのだが、原因が除かれない限り効き目はない。目の中のごみをそのままにして目薬をさすようなものである。訪問看護師とも相談し緩下剤を切ったことがあった。ところが幾日かして往診の途中ヘルパーから連絡があった。彼女が腹痛でうんうん唸っているという。立ち寄ると、さぞ嬉しかったのだろう、私を見て泣きべそをかいた。咄嵯に
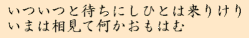
を思い出した。死の床にある良寛が、若くて美しく優しい貞心尼の顔を見たときの歌だが、こちらはひょっとすると老婆の便を指でかき出す可能性があったのである。
私の医学生時代、高齢者で腹痛があり便秘と下痢が交代するときは大腸がんも疑えと教えられた。しかしお年寄り(自分を含めて)は、症状を伝えるのでもくどくどと余計なことを並べ立てて、「結局何をいいたいんですか」と聞きたくなることも多い。その点、良寛さんが寺泊の医師宗庵に宛てた手紙を読むと実に簡潔明瞭で要を得ている。教科書に引用したいくらいの名文である。
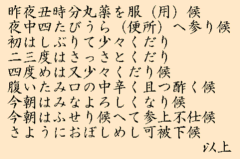
どうです、こんな病状報告ができたら胸がすっきりするのではないか。
とはいうものの現在の日本では、良寛みたいなはっきりした症状が出るまで大腸がんをほうって置くことは少ない。大腸鏡の利用と技術では日本は世界一であろう。しかしかつて手術もできない時の苦しみは昔の人が伝えてくれる。
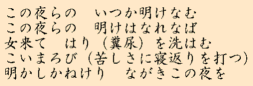
終末期医療でもっとも重要な手当は病者の苦痛を取ることであるのは言うまでもない。介錯の目的は苦痛を取るためにいのちをさえ絶つのである。そういう信念である五十代後半のガン性腹膜炎の患者をケアし、モルヒネの量をどんどん増やしていったことがあった。ところが一日千五百ミリグラムまで増量したら、彼はもう増やさないでくれと懇願した。麻薬はありがたい。が、それを打つと眠たくなる。彼は眠っている間の死を恐怖したのだった。それぞれの病者から何かを学ぶ。
良寛は死に臨んで薬もご飯もロにしなくなった。貞心尼が自分でいのちを縮めているのかと聞くと、いや休息してその時を待っているのですよ、と答えた。
私が終末期医療で学んだことも、やはり彼の手紙に尽きている。
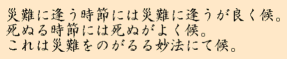
Que Sera Sera VOL.50 2007
AUTUMN
|
![]()