|

元国立環境研究所所長 大井 玄
高齢者人口が増えたせいか、認知能力の衰えを感じさせる人がずいぶん増えてきた。これ、自分の呆け具合を弁護する意味合いもある。
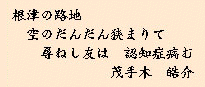
認知症の人が増えると同時に、そのような人たちを隠さず医療の助けを借りるのが当然、という風潮も出てきている。なにしろ「物忘れ外来」さえつくられている昨今だ。
三十年も昔、長野県佐久市で「寝たきり老人呆け老人」の宅診に携わった頃、「呆け老人」はまだ家に隠されたりもしていた。当時認知症が気づかれる典型的な発端は、嫁が自分の財布を盗ったなどという被害妄想をおばあさんが抱き繰り返し騒ぐものだった。嫁は姑の性格が急に変わり意地悪になったと戸惑ったりする。やがて他人迷惑な言動は、おばあさんの記憶力が低下し、自分がちょっと前にしたことを憶えていないためだと解る。しかしその頃には、おばあさんは孫さえ寄ってこないほどに孤立している場合があった。
認知能力の衰えについて一般の理解が進み、それが生老病死の一つと認識されたならば、いたわりの気持ちが生じるのもまた自然である。近年若い人たちにそれが見られるのはうれしい。
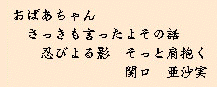
作者は高校三年生。かしこくて優しいに違いない。
アルツハイマー病の人たちが施設でてんでんばらばらな話をしながら、それでもごく楽しそうに語らっていることがある。お互いに通じない話であり、「偽会話」として知られる現象だが、その萌芽は家庭でも見られる。
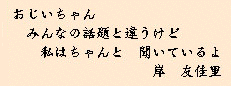
やはり高校三年。注意深く思いやりのある娘さんであろう。
記憶を中心とする認知能力は、自分の置かれた世界とつながっているという感覚を維持するため必要である。その衰えが実存的不安を生ぜしめるのは仕様がないとしても、衰えを受容してしまうならば、それはそれで新しい局面が開けて来ることもある。
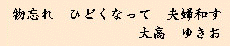
とか
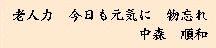
など、川柳が少し涙の味のする笑いの世界を展開してくれる。
外来で心配事の相談を受けていると、老いに伴う衰えの受容は、性格、経歴、家庭環境などいろいろの要因に関わっているものの、最後にはその人生観あるいは人生に対する覚悟に係ってくるようにも見える。普通の意味での頭のよさや社会的地位ではない。
またある人が呆けても、本人は病識があるのかないのか比較的平然としていたりする。苦労するのは連れ合いだということになる。ある中小企業の社長が脳動脈瘤の手術を受けたあと急に呆けた。しかも「仮想現実症候群」と呼んでもいい症状を現わし始めた。この症候群では、病棟などを自分の働いていた場所と勘違いする。入院先の病室で患者たちがベッドで寝ているのを見て彼は怒鳴った。「みんな起きろ!真昼からサボッテいてどうする!」
この方は施設に入れられても威張っておられた。しかし転倒して大腿骨骨頭を骨折して自宅に戻った。奥さんが献身的にケアをしてあげるが、認知能力は衰えるるばかりである。あるとき大小便を粗相してしまい騒いだ。奥さんが駆けつけて始末をしてあげると彼は言った。「母さんすまない。肝心の時にうちの奴どっかに行っちまって居ないんだから」。
物事の認知と記憶は、世界と自分をつなぐ作用を果たす。年とともにその能力が衰えたとて、暖かでのんびりした、しかも敬老精神の厚い環境では、ストレスを感じぬままに「純粋痴呆」として終末期を歩むことが可能である。すこし前までの沖縄や、ベトナム、タイなどにその環境が残つている。
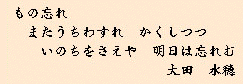
そんなのんびりした終末期を過ごしたいと願う気持ちは、年を取るにしたがって、濃くなるばかりである。
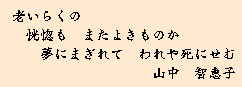
まずは恍惚を許容してくれる環境作りが私の課題であろう。
Que Sera Sera VOL.52
2008 SPRING
|
![]()