|
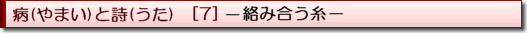
元国立環境研究所所長 大井 玄
老年期を歩むことは、臨床医として患者さんの訴えに耳を傾けるせいもあろうが、生きる営み自体が次第に重く、しかも宙に浮いたように感じる過程であるようだ。腰や膝に重い感じがある。早く歩こうにも脚がいうことを聞かない。かつて楽に開けたビンのふたが開けない。靴を履こうとするとバランスが崩れる。夜、小用に立つ回数が増える。起床しても寝足りない感じが残る。便通の不順等々、それ一つでは些細な症状である。しかし、全体としては、歩く道の泥濘が次第に深くなるようで、そのくせ生活感覚は薄らいでくる。親しい友の死は、世界とのつながりが絶たれるような感覚さえ起すのである。
高校同期の友人にOがいた。色のあさ黒いジャガイモみたいな顔つきで、ずんぐりとがっしりの中間のような体型だった。サッカー部で一緒にボールを蹴ったのだが、運動神経の鈍い私にさらに輪をかけた不器用な男だった。鈍足、キックカのなさ、球捌きの鈍さ、反射行動の拙劣さでわれわれは双壁だった。二人は左右のハーフバックだったが、すこし上手い相手には手もなくひねられた。サッカー部の先輩コーチには、そういうわけで、とくに「可愛がって」もらった。グラウンドを何周かして頣を出しているわれわれは、ご褒美として、僚友より多くもう一周させられたのである。
ユニフォームを脱いだOは、大人びた苦労人の雰囲気があり、揉め事のあるときなにかと仲裁役を買って出た。敗戦から十年も経たぬ貧しい時期であり、家庭もともに貧しかったから、ときどきそばやラーメンをおごりあうのが、いわば、われわれの連帯感の表明であったのだろうか。そう、食べるものはどんなものでも美味かった。
われわれは大学も、卒後の進路も大きく違った。しかし受験に何度も失敗し浪人生活を何年も繰り返す鈍重さは、サッカーをやった頃を再現している様子があった。だがその後、彼は新聞社に入り、晩婚ではあったが年のずっと若い賢く美しい人を貰い、最後は労務担当の重役になった。重厚な風貌で頷きながら、タバコの煙が濃い飲み屋で部下の話を聞いてやる様子は、いわば伝統的日本社会での人と人のつながりの暖かさを伝えていた。
年に何回か、高校時代からの友人数人と飲む会で、彼から肺がんに罹っているのを打ち明けられたのは、確か七年まえだった。
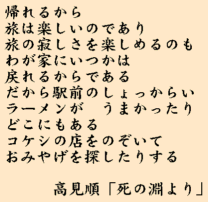
結局、闘病というほどの闘病もしないで、彼はあっけなくあの世に旅立った。人生の守備もサッカーに似て下手だった。
人は、どんな時、人生の答えを見つけたと感じるのか。人生は、様々な色の糸が限りなく絡み合ってできているように見える。細部では模様があるようでも、全体としては漠とした霞のように広がる景観である。糸の色は、仕事、友人、仇、趣味、宗教、健康等々その人の関心の数だけ存在する。
高校二年夏、サッカーの合宿は、長野県のある中学校グラウンドを借りて行われた。そこは桜の並木に囲まれ、直ぐ横では千曲川の清流が涼しい音を立てていた。炎天下でいがくり頭でボールを追うだけでも、汗は目に入りのどが渇く。しかし当時の奇妙な精神主義的鍛えは、できるだけ水を飲むなというものだった。飲むと反って疲れが増すといういかにも非科学的説明が付いていた。
練習の仕上げには、チームがグラウンドを何周か走る。こちらは疲労と脱水ですでに頭が朦朧としている。喘ぎ喘ぎ走る横にはOも負けじと、しかしどたどた駆けている。コーチの先輩は校舎の日陰に座ってその様子を見ているが、最後の一周では彼も加わり先頭に立ち、いとも軽々走るのだった。練習の後、百メートルも離れていない宿屋にたどり着くのも難行だった。合宿が始まった数日後、韓国からの留学生が疲労のあまり脱落した。その彼ももう亡くなっている。
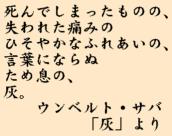
友人Oという糸を手繰るだけでも、それは無数の様々な糸と絡み合い、またほどけ、また絡み合うのが見えてくる。私という糸ももう直ぐほどけるのだろう。だが漠たる人生には、漠たる満足があるのも、確かである。
Que Sera Sera VOL.53
2008 SUMMER
|
![]()