![]()
ココロが原因ではなかった
![]() パニック障害の正体
パニック障害の正体
バスで電車で突然、激しい発作が起きる病気、パニック障害。どうやら正体は「心」にではなく「脳」に潜んでいるらしい。
東京ドームのアリーナで、突然の大音響と「キャーッ」という大歓声が耳をつんざいた。
瞬間、ケンジさん(40)は、ガタガタと震え、過呼吸が始まった。異状を察した係員に付き添ってもらい、場外へ。外の空気を吸ううちに症状は治まったが、場内に戻るとまたぶり返す。結局、ライブが終わるまで外で妻を待っていた。5年前、妻の誘いで出向いたライブの会場でのことだった。
本格的に発作が出たのはその数年後だ。帰宅途中のJR東海道線の品川から大船までノンストップの通勤快速に乗っていた。つり革につかまり、次々と視界を走り去る通過駅を見ていると、胸騒ぎのような感覚がこみ上げ、一気に動悸が激しくなった。
苦しさに顔をゆがめながらじっとがまんした。
その後は東海道線に乗るたびにこの発作が起きるようになり、目的地にたどりつくまでに5回も6回も途中下車。やがて東海道線には乗れなくなり、「発作が起きるのでは」という恐怖で地下鉄や地下道、エレベーターにトンネルと、行けない場所が増えていった。

マコトさん(35)の発作の前兆は浪人中の大学受験会場だった。滑り止めの大学の試験中、緊張でたびたびトイレに立ち、全く集中できなかった。次の試験から開始2時間前に会場入りして席を確認し、監督官に相談して席替えをしてもらったが、それでもトイレに立つ。結局、4大学5学部の試験すべてで同じ状態だった。
何とか志望校に合格し、しばらく体の異常は感じなかったが、就職後の99年の春、職場が新体制に変わり、マコトさんも積極的に激務に取り組んだ。連日、終電を逃す時間まで働いては近くのサウナで仮眠、また仕事という生活が数カ月続いた。
疲労がピークに達した頃だ。電車に乗ろうとして「嫌な感じ」がこみ上げてきた。乗ると、呼吸が速くなり、手のひらに汗をかき、トイレに行きたくなった。通勤に使う地下鉄も、混雑時は乗れない。妻の誘いで渋々と向かう映画館も、出口の近くの席以外には座れない。
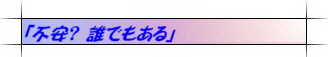
最近では床屋でも発作が起こりそうで、知り合いのスタイリストに相談して、出張料金で自宅に来てもらうことにした。
「妻は、何もそんな無駄遣いしなくたっていいじゃないというんです。健康な人たちは理解できないですよね。普通に見える人間が電車に乗れなくなるとか、床屋に行けなくなってしまう病気にかかっているなんてことが」
電車、地下道、バス、コンサート会場、トンネル、高層ビル、映画館、床屋、交差点、横断歩道、スーパーのレジの列……。
あらゆる場所で、ある日突然、激しい動悸や息切れ、震えといったパニック発作にみまわれ、再びの発作を恐れて行動範囲がどんどん狭まっていくのが、パニック障害(PD)患者の特徴だ。現在、日本には100人に3〜4人の割合で患者がいるといわれ、他の不安障害と診断されている人など、潜在的なPD患者数を含めるとさらに多いとみられている。
1992年に世界保健機関(WHO)がPDを国際疾病分類として認知して以後、日本でも徐々に認知されてきた。しかし、過呼吸と診断されたり、症状が進んだ後の「うつ」だけを診断されたりするケースが絶えない現状もある。
患者同士の自助グループ「全国パニック障害の会」理事の五十嵐容子さん(51)は、二十数年前に発症。流産直後に夫の急な転勤が重なり、不安を募らせていたタイミングだった。長い間、病名がわからないまま、婦人科や精神科を転々。ある医師はこう言った。「若年性更年期障害だよ。もう一人産んだら、ホルモンのバランスがよくなるから産むといい」
そうすすめられて第2子を出産。しかし快復せず本格的に発作を発症。別の医者に、強烈な不安に悩まされていると相談すると、
「不安?そんなものは誰にでもあるじゃないか。あなたに根性がないからだろう」
と、一笑に付された。
結局、五十嵐さんは家族が見つけてくれた医学書に自分と同様の症状が載っていたことから、神経症患者自助グループに参加。PD治療に取り組んでいた都内の医師も見つけ、本格的な治療にたどりついたという。
自らの苦労から、五十嵐さんは患者同士の憎報交換を大切にしている。誤診や、体質にあわない薬物投与を防ぐのに役立つからだ。
五十嵐さんはこう語る。
「患者の側から見れば、誤った薬物投与を続けている医者は各地にいます。特に地方には、知識を更新する意欲のない医師すらいる」

こうした医療現場でのばらつきを最小限に抑えようと、厚生労働省は2004年度、複数の医療専門家による「パニック障害研究班」を結成。臨床研究を基に、治療ガイドラインの策定をすすめている。現段階のガイドライン試案では、意外なことにPDを「本人の性格や気のせいではなく、不安・恐怖に関係する脳の機能障害」であると断定している。主任研究者の熊野宏昭東京大助教授はこう語る。
「PDが心の病気か脳の病気かという問題は確かに難しいものです。しかし薬が大変よく効くこと、そして患者の脳の異常が明らかになってきている点から、脳の病気といえる要素が濃くなってきていると言えます」
確かに、自宅で就寝中や家族と共にテレビを楽しんでいる最中といった安静時の発症例も少なくないなど、不思議な点が多かった。この謎が、研究班の研究で、徐々に明らかになってきている。
03年、東大グループが、PET(陽電子放射断層撮影)装置で患者と健常者の脳の活動を画像化して比較した。患者の脳は、安静時でも不安や恐怖といった記憶をつかさどる扁桃体や、不安や恐怖を体験した状況の記憶をつかさどる海馬などが健常者より活発に活動していることを突き止めた。
一方近年、米国の研究グループがラットを使った動物実験などで、この扁桃体における不安や恐怖の学習記憶がどのようにして消えていくかを解明。その結果、ただ忘れるのではなく「新しい学習による上書き」の機能が、恐怖体験に打ち勝つ重要なキーワードであることが分かってきたという。

ラットにブザーを合図に電気ショックを与える。何度かこの「苦行」を経たラットは、ブザーを聞くだけで体をすくめて動かなくな
る恐怖反応を示すようになるが、次にブザーをならすだけで電気を流さない状態を何度か繰り返す。するとラットはブザーを聞いても平然としているようになる。ところがその時に、前頭葉の内側面のある部位を破壊しておくと、平気になったはずの恐怖反応がよみがえってきたという。熊野助教授が解説する。
「ブザーと電気ショックという一連の恐怖条件が脳内に記憶されても、その後に『電気が来たときと同じ状況だけど、大丈夫だ』という事実を学習し直すことで、記憶が上書きされているらしい。この上書きデータが、扁桃体などに蓄積した恐怖の記憶を押さえ込む働
きをしていると考えられ、その機能が前頭葉の内側面にあることが示されました」
PD患者も、何らかの形で、パニック発作を引き起こした場所や状況を見ても「大丈夫なんだ」という記憶が脳に上書きされれば、不安も発作も起きなくなることになる。
快復の鍵を握る前頭部を、いま流行の「脳グッズ」で鍛えまくればいいのかというと、そうではないらしい。
米国の精神科医が00年に発表した、こんな調査がある。
PD患者を5グループに分け、それぞれ治療法を、
①抗うつ剤
②薬を使わない心理療法
③抗うつ剤と心理療法
④何も効用がない抗うつ剤の偽薬
⑤偽薬と心理療法
に分け、治療経過と再発率を調べた。すると、治療経過は④だけが飛び抜けて悪いだけで差異がなく、再発率は、②と⑤のグループがより低かった。心理療法に効果があったのだ。
心理療法は「認知行動療法」とも呼ばれ、PD患者がパニック発作が起きる状況に段階的に慣れながら、心理的なセルフコントロールにより発作を抑える方法だ。
熊野助教授率いる研究班は、この米国の結果を重視している。
「一見シンプルな治療法ですが、我々の研究でも行動療法の後に前頭葉内側の活動が高まる結果が出ており、脳に新しい記憶を上書きする力を鍛えることを実証しています。ガイドラインでは、行動療法の重要性も訴えていきたい」

前述の「会」の会員谷亀律子さん(52)の経験は、それを実証するものかも知れない。
10年来、PDと闘い、様々な症状を克服してきた谷亀さんだが、どうしても鉄道は各駅停車以外乗れなかった。ところが昨夏、甲府市に行く所用ができ、思い切って特急列車に乗ってみた。
発作が始まることがわかっていたため人目につかない車両の端の席に座り、背中を丸めて脂汗を流しぶるぶる震えながら、発作と闘うこと約1時間半。甲府駅に着いても、駅前の喫茶店でしばし震えが止まらなかった。
驚いたのは、帰りの特急だ。
「すごいんです。緊張はしたんですが、恐怖心が消えて、発作も起きなかったんです」
PD治療に詳しい医療法人和楽会の貝谷久宣理事長はこう語る。
「行動療法がPDによく効くことは臨床的にも明らかになってきているところで、実際、我々もネットを利用するなど様々な形で行動療法を採り入れています。ただ問題は、行動療法の実践家が非常に少ないこと。早急な育成が求められています」
(文中カタカナ名は仮名)
医療法人 和楽会
理事長 貝谷久宣