![]()
![]() 映画「阿弥陀堂だより」を観て
映画「阿弥陀堂だより」を観て
医療法人
和楽会 理事長
貝谷 久宣
赤坂の診察で1年前まではクリニックヘ来診する以外は一人でほとんど外出したことがなかったAさんが、「先生!パニック障害の映画を観てきました」とうれしそうに報告してくれました。「えっ!今そんな映画やっているの?」とわたしは聞き返しました。「そうなんですよ、先生!樋口可南子が演ずる女医がパニック障害になって田舎に引っ込んで療養し、病気が治っていくという映画です」とAさんは教えてくれました。早速、次の日曜日、わたしは新宿の武蔵野館に朝一番で出向きました。朝早かったせいか、中年の夫婦連れの観客が三々五々座っているだけで、ゆったりと一番よい席に座ることができました。
物語の概略を述べよう。寺尾聡扮する作家の上田孝夫と女医の美智子の夫婦が、孝夫の故郷である奥信濃の山村に移り住んだところから映画は始まる。夫は新人賞を取ってから泣かず飛ばず、妻は医療の第一線で活躍するうちにパニック障害にかかってしまった。二人は仕事と大都会の生活の疲れを癒し、パニック障害を治すために自然の懐に戻ったのだった。美智子は週に3日だけ無医村であった村で診療を始める。孝夫は主夫としてかいがいしく家事に精を出すとともに、村のボランティアも引き受ける。美智子の医者としての腕は確実で村人の信頼を得ていく。美智子達は村の死者が祭られている阿弥陀堂を守る96歳になる老婆おうめ(北林谷栄)をしばしば訪問するうちに、喉の肉腫を患い声が出なくなった少女小百合に出会う。小百合が人生の達観者であるおうめ婆さんの含蓄に富んだ言葉を聞き書いたものが村の広報誌に連載されている。そのコラムがこの映画のタイトルとなった「阿弥陀堂だより」である。おうめ婆さんの言葉の一部を引用しよう…「雪が降ると山と里の境がなくなり、どこも白一色になります。山の奥にあるご先祖様たちの住むあの世と、里のこの世の境がなくなって、どちらがどちらだか分からなくなるのが冬です。春、夏、秋、冬。はっきりしていた山と里の境が少しずつ消えてゆき、一年がめぐります。人の一生と同じなのだと、この歳にしてしみじみと感じます」。美智子夫婦の村の生活でもう一人ポイントとなる人物がいる。孝夫の中学生時代の恩師である幸田(田村高広)である。彼は自分が胃ガンの末期状態であることを知りつつ、医療を拒否し、書に精魂を傾け、潔く死を受け入れるべく端正な日々を送っている。幸田の生き様はまさにパニック障害者の病的心性の対極状態である。不治の病を慌てず騒がず天命として受け入れ、一日一日を自分流に精一杯生きる姿はパニック障害者の鑑である。美智子が看取る幸田の臨終の場面はこの映画のクライマックスの一つである。“死”があれば死からの脱出の“生”がある。
小百合の肉腫が転移していることを発見した美智子は、自分の執刀で手術をする決心をする。この成功を契機に美智子はパニック障害からの回復を自覚し、医者としての自信を取り戻す。それと相前後して、43歳になった美智子は再度の妊娠を孝夫に報告し、映画は「THE END」となる。
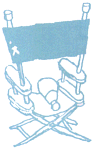
さて、映画の中のパニック障害について述べよう。映画に出てくる最初のパニック発作の場面は、美しい夕焼けのなかを二人で歩いているときに、突然の鳥の鳴き声におびえた美智子が、それをきっかけにして呼吸困難の発作を起こしたものである。映画の中で表現されたパニック発作は、この病気を知らない観客にとっては一瞬何が起こったのかと思わせる程度で、決して観客に不快な感じを与えるものではなかった。息をあらげる妻に優しく寄り添って身体を摩る孝夫の態度は、決して大げさではなく、ごく自然な振る舞いに見えた。物静かにそっと妻に気づかい続けるこの人物はパニック障害の妻にとっては最高の伴侶であり治療者でもある。「今までは息せき切って走ってきたから、のんびりしよう」と妻を優しいムードで包み込む。美智子にとって一緒にいるだけで心が安らいでいく夫である。孝夫に渓流つりにつれていかれ、一匹だけ釣れたイワナをいろりで焼いて食べるシーンがある。イワナの骨酒を飲んだ美智子は上機嫌になり、田舎生活の楽しさを見せてくれる。この夜から美智子は服薬することを止め、この村へ来てよかったと喜びを述べる。このシーンもパニック障害の経過を見せるこの映画の一つの山場であろう。二回目は小百合の治療方針を決めるときに緊張のあまりパニック発作が出てしまう。総合病院に泊まりがけで小百合の治療に当たる美智子は自分を信頼してくれる若い医師にパニック障害についての告白をする。パニック障害映画としてこの映画を見るときはこのシーンも一つのクライマックスとなる。美智子が自分の体験を若い医師にうっすらと涙をうかべて告白する場面は、ガラス細工のように繊細なパニック障害者の感性がにじみ出ていた。樋口可南子の名場面であったと思う。筆者はこの映画の原作者が南木佳士であることを、パンフレットを買い客席に座るまで知らなかった。南木先生の原作ならばパニック障害という病気が出てきてもおかしくないし、「阿弥陀堂だより」が南木先生の小説であることに気づかなかったのは迂闊だった。というのは、芥川賞作家であり、パニック障害を患うこの内科医と筆者は平成11年6月18日に佐久総合病院の応接室で対談をしているからである(この内容は日本評論社版“パニック障害に負けない”に掲載されている)。南木先生は、医師としてのパニック障害の経験をこの阿弥陀堂だよりの主人公である女医 上田美智子に託して語らせている。南木先生は300人前後の患者さんの死を看取ったと聞いているが、美智子は50人前後の患者さんの臨終に立ち会ったということになっている。最後の患者さんを看取って自室に帰り雲を見ていたら、自分の気が抜き取られていく感じがしたと原作者は主人公に語らせている。美智子の発病は死との直面と流産という不幸が重なって生じたと考えられる。パニック障害は"死を恐怖する病"であると言うことを知ればこの発病状況も納得できる。
この映画は、新緑の美しい林、幻想的な夏の灯籠流し、ススキがなびく棚田の風景、千曲川の背にそびえる雪の山々など穏やかで、優しい信州の四季を美しく描き見せてくれる。また、村の小路を歩く素朴な人々、“夕焼け子やけ”を歌い家路につく子供達、阿弥陀堂に集まり念仏を唱える村人達は見る人の心に郷愁を呼び、なんともほっとさせてくれる。この映画は主人公のパニック障害が治っていく過程を見せてくれるだけでなく、大自然、ゆったりした時の流れ、人柄のよい人々、これらがこの映画の大きな流れとなって観客のパニック障害をも癒してくれる映画であると筆者は思った。
ケ セラ セラ<こころの季刊誌>
VOL.31 2002 WINTER